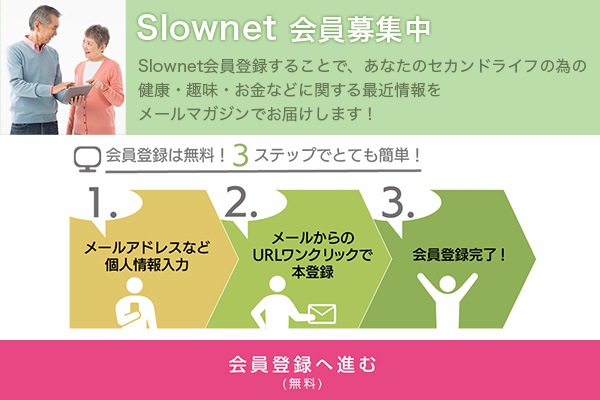節分はいつ?コロナ流行中の節分はどのような感じになる?
気がつけばもう明日で2月がスタートします。
2月最初のイベントといえば「節分」ではないでしょうか?
今年の節分は新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、どのような変化を迎えるのでしょうか?
また今年は、124年ぶりとなる珍しい節分でもあります。
今回は新型コロナウイルス感染症拡大が続いている中、節分を楽しむ方法についてご紹介します。
今年の節分はいつ?節分の由来&歴史は?

画像提供:imagenavi(イメージナビ)
ご存じの方も多いかもしれませんが、まずは節分の由来や歴史から見ていきましょう。
節分の起源とは?
「豆をまいて鬼を払って福を呼び込む日」。
節分に対して上記のようなイメージをお持ちの方も多いではないでしょうか?
また、後述しますが最近では「恵方巻きを食べる日」でもありますよね。
鬼を払う節分という行事は歴史が古く、平安時代に遡ります。平安時代の宮中行事である「追儺(おにやらい)」が起源だそうです。
平安時代、追儺は12月の大みそかに開催されていました。
方相氏(ほうそうし)と呼ばれる鬼役が手下役の役人を引き連れて宮中を回り、厄をはらっていたのだそうです。
方相氏という言葉は聞き慣れませんが、鬼神のこと。金色の目を4つ持ち、朱色の衣裳を身にまとって盾と矛を持っているのだとか。
起源から分かるとおり、元々は厄をはらう存在でした。恐ろしい姿をして、本当の鬼を追い払う、というのが始まりです。
ところが9世紀頃、見た目の恐ろしさからか悪鬼としてみなされるように弓矢で追い払われる存在となってしまったのです。
この当時、疫病などは鬼が原因、鬼がとりついているなどと言われていたことから、鬼を弓矢で追い払い、病の流行を封じ込める、といった意味合いだったそうです。
豆まきはいつから?
当初は弓矢で追い払っていた節分。現代では豆まきを行いますよね。豆まきが行われるようになったのはいつ頃からなのでしょうか?
豆まきは元々中国の風習だったそうです。時期としては明(1368年〜1644年)の頃なのだとか。
この風習は室町時代頃日本に伝わり、年男が「鬼は外、福は内」と言いながら炒った豆を蒔いたそうです。
地域によっては節分のことを「年取りの日」とも呼び、この日にひとつ年を取ると考えていました。
こうした考え方があったため、年の数だけ豆を食べる、という文化も生まれたそうです。
炒り豆を巻く理由
多くの地域では炒った大豆を巻くのではないでしょうか?
北海道や東北、九州など一部地域では落花生を巻いたりするそうですが、まだまだ炒った大豆を巻く地域が多いそうです。
炒り豆は「火を通した豆」のこと。悪い鬼を寄せ付けないように巻いた豆から芽が出る(=悪いものが根付く、育つ)ということを嫌い、炒った豆を蒔いたことが始まりだそうですよ。
そもそも節分とは?
それではここからはそもそも節分とはどのようなものなのか、歴史を詳しく見ていきましょう。
節分は「立春」の「前日」というのが本来。
そのため、節分を知るためには立春の日はどのようにして定められているのかを知ることが大切です。
立春は季節のひとつを指す言葉。春夏秋冬で表現することが多いですが、1年を24分割した「二十四節気(にじゅうしせっき)」という考え方を日本は古来、持っていました。
二十四節気の代表例をあげると、春分、夏至、秋分、冬至などが当たります。
これらは現代でも気にされる方が多い日ですよね。特に春分の日、秋分の日は祝日に定められているので意識する機会も多い日でしょう。
二十四節気は地球と太陽の位置関係で決まるのが特徴です。太陽と地球は常に自転と公転を繰り返し、1年周期で位置関係が変動します。
そのため、夜と昼の時間が一緒の「春分」「節分」のほか、昼がもっとも長い「夏至」、夜がもっとも長い「冬至」といった日が生まれるわけですね。
また、地球から観測した太陽の位置で二十四節気は決まっています。
おおよそ15日経過ごとに新たな節気がやってくる、というわけです。
実際に1年は約365.2425日であるため、年によって日にちが若干前後するというわけですね。
二十四節気
では、二十四節気はどのようなものがあるのでしょうか?
1年の最初にやってくるのが冬です。
この冬の期間は「小寒」(1月6日)、「大寒」(1月20日)という季節があります。
2月に入ると、季節は春。
「立春」(2月4日)、「雨水」(2月19日)、「啓蟄(けいちつ)」(3月5日)、「春分」(3月20日)、「清明」(4月4日)、「穀雨」(4月19日)が春の季節。ただし、立春は1年で一番寒い季節です。一般的には立春を越えると、徐々に暖かい日が増えて春が近づいてきます。
続いて夏は「立夏」(5月5日)、「小満」(5月20日)、「芒種」(6月5日)、「夏至」(6月21日)、「小暑」(7月7日)、「大暑」(7月22日)。
秋は「立秋」(8月7日)、「処暑」(8月23日)、「白露」(9月7日)、「秋分」(9月22日)、「寒露」(10月8日)、「霜降」(10月23日)。
冬は「立冬」(11月7日)、「小雪」(11月22日)、「大雪」(12月7日)、「冬至」(12月21日)となります。
日付を見てみると、祝日ではないものの「○○の日」と定められ、現代でも残っている日がありますよね。
節分の意味・由来
さて、季節がわかったところで改めて「節分」について考えていきましょう。
漢字からも分かるとおり、節分は「季節の分かれ目」という意味。
つまり、「立春」「立夏」「立秋」「立冬」が「節分」に該当します。
しかし、現代では節分といえば「立春」の前日のみを指しますよね。
これには諸説ありますが、1年の始まりを春からと定めていた昔の名残だと言われています。
つまり、現代の大晦日に相当する日が「立春」の「前日」なのです。
そのため、1年の締めくくりを祝う、特別な日と捉えられていたそうです。
2021年は124年ぶりに2月2日が「節分」
今年、2021年の節分は1897年(明治30年)以来、124年ぶりに2月2日が節分です。
国立天文台のサイトにはより詳しく記載されているので、興味がある方はぜひ覗いてみてください。ここでは抜粋してご紹介いたします。
上でご紹介しているとおり、節分は2月3日と定められているわけではなく、立春の前日です。多くの年ではこの日が2月3日にあたります。
しかし立春はそもそも2月4日に固定されているわけではなく、年によっては3日だったり、5日だったりします。
前述の通り、地球が1周するのにかかる時間は365.2425日。つまり1年で6時間ほどのズレが生じます。このズレを解消すべく、4年に1度程度あるのがうるう年ですよね。
同様に地球が立春の位置を通過する時間単位で見るとこちらも若干のズレがあるそうです。そのため、立春の日付は前後してしまう、というわけです。
立春の日が動くと節分の日も合わせて動くので、年によっては2月4日だったり、2月2日だったりします。
このズレを調整するため、2022年は2月3日に戻る節分ですが、2025年から4年ごとに2月2日が続いて、世紀末に向けて頻度が上昇するそうですよ。
======
生活にお役立ちの情報がメールマガジンも受け取れる!【無料】Slownet会員登録はこちらから↓
>>次ページ 節分は何で恵方巻を食べるの?
-
2025年3月17日
-
趣味・文化
シークワード(9)
シークワード 難易度:★★★☆☆ 漢字3文字の言葉を10個探してください。 言葉はタテ、ヨコ、ナナメのどれか一直線で読めるものに限ります。1つの文字を複数の言葉が共有する場...
-
2024年9月12日
-
趣味・文化
イラストクイズ(12) 「お月見」
イラストクイズ 難易度:★★★☆☆ 上のイラストと下のイラストで違うところが五つあります。 解答を見る イラストクイズ 解答 ...
-
2024年8月23日
-
趣味・文化
背筋がゾクッ! 怖~い怪談
夏ともなれば、肝試しにお化け屋敷、ホラー映画などが人気を集めます。中でも、落語や講談、歌舞伎などの「怪談」は、背筋がゾクッとするような話ばかり。暑い夏の夜は「怪談」で涼んでみません...
-
2024年7月29日
-
趣味・文化
四字熟語分解クイズ(11)
四字熟語分解クイズ 難易度:★★★★☆ 漢字のパーツを組み合わせて四字熟語を作ってください。 解答を見る 四字熟語分解クイズ 解答 ...
-
2024年3月1日
-
趣味・文化
四字熟語リレークイズ(9)
四字熟語リレークイズ 難易度:★★☆☆☆ 下の□に漢字を入れ、漢字4文字の言葉を完成させながら、スタートからゴールに進み、四字熟度リレーを成立させてください。矢印でつながって...
-
2024年2月15日
-
趣味・文化
四字熟語分解クイズ(10)
四字熟語分解クイズ 難易度:★★★☆☆ 漢字のパーツを組み合わせて四字熟語を作ってください。 解答を見る 四字熟語分解クイズ 解答 ...