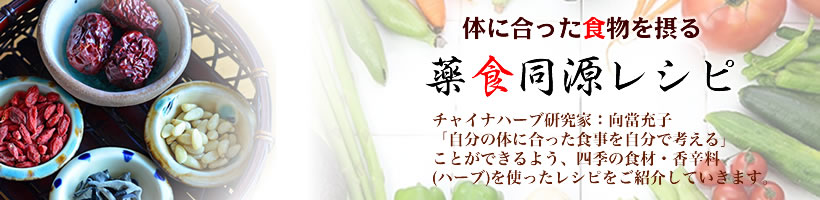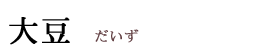もっと大豆の力を! – 体にあった食物を摂る「薬食同源レシピ」第21回

<マメ科ダイズの種子。写真は黒大豆と黄大豆>
●もっと大豆の力を!
大豆は、豆腐、納豆、味噌など日本の食生活になくてはならないものです。古くから薬用としても使われてきました。上記は黒大豆の薬効です。
黄大豆は脾・胃・大腸系に入り胃の働きを助けますので、疲れたとき、また病後の回復を助けます。疲れたときの味噌汁が格別なのもうなずけます。
近年イソフラボンの女性ホルモン様作用が期待されていますが、古来、婦女の陰虚によるめまい、月経不調に黒大豆が使われていました。更年期の前から食べ続けることが大切と思われます。
少し前まで日本の食卓にはさまざまな豆の煮物が大切に作られていましたが、子どもたちに伝わっておらず、少なくなっているようです。煮物にするだけでなく、いろいろな豆と混ぜて茹で、サラダにしたり、ポークビーンズ、スープにしたり、洋風料理が知られるようになっていますのでもっとたくさん食べてもらいたいと思います。
ちなみに黒豆衣(こくずい)は黒豆の種皮です。
[レシピ] 豆ご飯


- 米
- 1.5カップ
黒豆、大豆、小豆、緑豆、インゲン豆、ひたし豆、南京豆など適宜ですが、豆類は全部で0.5カップ適宜ですが、豆類は全部で0.5カップ

1. 大きな豆類は12時間くらい水に浸けておく。水煮、ドライパックの豆を使うと便利です。
2. 豆類は柔らかく煮ておく。大きな豆から煮始めて小さい豆を足していくと 綺麗にできます。
3. 米は洗って30分以上浸けておく。
4. 米を炊きます。沸騰してきたら豆を入れて炊きあげます。
緑豆は米と一緒に炊き始めても柔らかくなります。
☆次回は「枸杞(クコ)」のお話です。どうぞお楽しみに。
======
Slownetでブログやコメントを更新すると同じ趣味の仲間が見つかるかも!?人気のサークル情報などをお知らせするメールマガジンも受け取れる、Slownet会員登録はこちらから↓
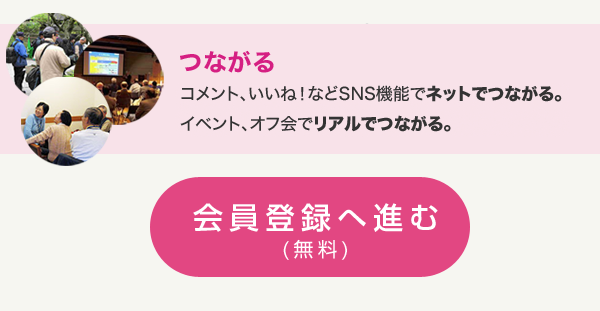
-
2025年3月24日
-
薬食同源レシピ
苦みパワーで不調を改善
人間や動物は寒い冬を乗り切るため栄養分を体にため込む傾向があり、春になると、余分となった栄養分は老廃物となって外に排出されます。独特の苦みをもった春の山菜は、老廃物を外に出す成分を...
-
2025年3月10日
-
薬食同源レシピ
ランニングで脳を活性化!記憶力・集中力アップの秘訣
ランニングは単なる運動ではなく、脳を鍛える効果もあります。研究によると、ランニングによって記憶力や集中力を高める「海馬」や「前頭葉」が活性化し、新しい脳細胞が生まれることが分かって...
-
2024年8月1日
-
薬食同源レシピ
野菜・フルーツの老けない食べ方
老化の原因には、食事や生活習慣、ストレスなどさまざまな要因が挙げられますが、最近注目されているのが体の“酸化”。野菜や果物は、体の酸化を防いでくれる強い味方です。栄養素の長所を生か...
-
2024年7月1日
-
薬食同源レシピ
真夏に備えて、“汗活“をはじめよう!
気温が上昇すると、汗をかく機会や量も増えてきます。汗は体温調節などの重要な役割を担っており、“良い汗”をかくことも暑い時季を健康的に乗り切るポイントです。真夏に備えて“汗活”を始め...
-
2024年2月2日
-
薬食同源レシピ
めまいや頭痛の引き金に 気象病とその予防
低気圧が近づくと腰痛や関節痛がひどくなったり、季節の変わり目に片頭痛が出やすかったりしたことはありませんか? 天気の変化で不調を感じたら、それは「気象病」かもしれません。 「...
-
2023年11月17日
-
薬食同源レシピ
インフルエンザを予防しよう! 冬のウイルス対策
新型コロナ感染症も気になりますが、この時期気になるのが、インフルエンザ。毎年12月から3月の寒い季節に流行のピークを迎えます。予防するためには、手洗いやうがい、マスクの着用を徹底し...
人気記事はありません