昼寝で認知症予防!毎日ぐっすり眠るために
「認知症にはなりたくない!」
どんな病気も嫌ですが、特に「認知症にはなりたくないなあ」というのが、シニアの本音ではないでしょうか?

画像提供:imagenavi(イメージナビ
認知症と睡眠時間の間には、関係があるそうです。
昼寝も認知症予防のひとつになるということ。
また、「昼間は働いているから」という方には、睡眠の質を高める方法をご紹介します。
睡眠は脳にできる「老人斑」を防ぐ
そもそも認知症には大きく分けて3つの種類がある、ということはご存知でしょうか?
ひとつはもっともメジャーな「アルツハイマー型認知症」。
アルツハイマー型認知症は、アミロイドβというタンパク質が脳に蓄積し、神経細胞が減少することで脳の萎縮が進行する病気のこと。
記憶障害が徐々に進行し、日付や曜日がわからなくなり、仕事の要領が悪くなっていきます。
症状は徐々に、徐々に、緩やかに進行するのが特徴です。
ふたつ目は「血管性認知症」。
脳梗塞、脳出血、くも膜下出血などの脳卒中が原因で起こる認知症で、脳卒中後の後遺症である歩行障害や言語障害を呈することが多く、仕事の容量が悪くなります。
特徴としては脳卒中を繰り返す度に悪化していきます。
対処法としては脳卒中の再発予防。
3つ目は「レビー小体型認知症」です。
レビー小体というタンパク質が脳に蓄積するため起こる認知症です。
他の認知症と一線を画す特徴が、実際には存在しないものや人物が見える幻覚(幻視)、人脈誤認が起こる点。
また、動作が極端に鈍くなり、転びやすいなどの症状が徐々に進行していきます。
調子の善し悪しがはっきりとしているのも特徴です。
このほか、前頭側頭型認知症、正常圧水頭症、慢性硬化膜下血腫、甲状腺機能低下症など、認知症にはさまざまな種類があるのです。
睡眠が特に効果的だとされているのが、アルツハイマー型認知症に対して。
アルツハイマー型認知症の引き金になると見られている脳内でのアミロイドβの沈着。
この沈着が起こると脳に「老人斑(アミロイド斑)」が生まれます。
動物実験段階ですが、対象の動物を断眠(眠らないように)すると、脳のアミロイドβの沈着が3倍に増えるというのです。
これらは研究段階でまだはっきりとはしていませんが、日中の活動で脳内に生まれたアミロイドβは、睡眠によって脳から排出される仕組みになっているよう。
そのため、よく眠ることが老人斑対策だと近年提唱されています。
しかし、年齢を重ねると眠ることが難しくなってきます。
「寝付きが悪い」「夜目が覚める」「夜間頻尿で度々眼を覚ます」という方も多いのではないでしょうか?
睡眠を促進するのは松果体ホルモンであるメラトニン。
このメラトニンの分泌は、年齢の増加とともに減少することがわかっています。
アルツハイマー型認知症では、メラトニンは更に減少してしまうため、より睡眠時間が短くなり、アミロイドβを排出できずに溜めていってしまう悪循環が生まれてしまうのです。
睡眠時間は年齢によって変化するもの。
欧米の調査では、5~10歳では平均8時間以上に対し、30~65歳は6時間台、70歳以上では5時間台という結果に。
このことから分かる通り、年齢を重ねたら、8時間睡眠を目指す、というのは人間の仕組み上無理があるのです。
夜の眠りが短い人は昼寝がお薦め

画像提供:imagenavi(イメージナビ
無理に夜の睡眠時間を増やすのはとてもむずかしいもの。
だったら、日中に睡眠を取る「昼寝」はどうでしょうか?
実は昼寝はとても効果的だと最近の研究でわかってきています。
夜に寝られない分は、昼寝でカバーすればよいのです。
ただし、昼寝も寝すぎると逆効果に。
60分未満の昼寝はアルツハイマー型認知症の発症リスクを下げ、60分以上はリスクを高める、ということもわかっています。
昼寝をする際は60分未満を心がけるようにしましょう。
こうした睡眠パターンは、自分に合った、もっともしっくりくるサイクルを見つけることが大切です。
●時に眠ると、朝○時くらいにスキッと起きられる、など自分自身に最適な睡眠サイクルを見つけましょう。
もし寝られない場合は、睡眠薬に頼ってももちろんOK。
読売新聞グループ本社主筆の渡辺恒雄さんは70年以上、毎日睡眠薬を飲み続けているそう。
睡眠薬を飲み続けているおかげか、認知症を発症しそうな雰囲気はまるでないのだとか。
睡眠の質は「黄金の90分」がカギ

画像提供:imagenavi(イメージナビ
最近「睡眠負債」という言葉をよく耳にするようになりました。
睡眠負債とは日々の睡眠が足りないことよって、心身に深刻なマイナス要因が積み重なっていく状態のこと。
睡眠負債が積み重なっていくことで判断力が低下するだけでなく、精神の健康を害してしまう可能性が高まります。
睡眠はしっかりととりたいものですが、具体的にポイントやコツなどはあるのでしょうか?
その答えは「黄金の90分」にあります。
人の眠りには「レム睡眠」(=脳は起きているが、体は眠っている状態)と「ノンレム睡眠」(=脳も体も眠っている状態)の2種類があり、一定周期で交互に入れ替わりながら人間は睡眠を取っています。
一般的にノンレム睡眠のほうが深く眠っているため、起こすのが難しいほど熟睡する人も多いそう。
人は入眠すると、まずノンレム睡眠が訪れます。
特に最初のノンレム睡眠は睡眠全体のなかで、もっとも深く眠るとされており、この段階の人を起こすのはとても難しく、無理に起きたとしても、頭がボーッとした状態で眼を覚まします。
この最初のノンレム睡眠が「黄金の90分」なのです。
ノンレム睡眠中の90分の眠りを、いかに深くできるかがポイント。
ここでしっかりと深く眠ることができると、その後の睡眠リズムが整い、自律神経やホルモンの働きが良くなり、翌日のパフォーマンスが向上します。
逆に、この最初の睡眠でつまづいてしまうと、どれだけ長く寝ても自律神経が乱れたり、日中の活動を支えるホルモンの分泌に狂いが生じてしまうのです。
睡眠に悩んでいる方は、入眠の最初の90分をしっかりと眠れるよう対策をすると良いでしょう。
90分の眠りの質を上げるポイントは「『体温』と『脳のスイッチ』」にあります。
体温には内部の体温である「深部体温」と手足の温度である「皮膚温度」の2種類があります。
深部体温は日中ほど高く、夜間に低くなりますが、皮膚体温は昼に低く、夜間に高くなるという特徴があります。
健康な人の場合、入眠前は手足が暖かくなり、毛細血管から熱を発散することで深部体温を下げます。
日中は深部体温と皮膚温度の差は2度ほどですが、入眠時は2度未満になり、差が2度未満になると人は快適に眠りにつけるそうです。
睡眠前にお風呂に入ったり、足湯に浸かったりなど、皮膚体温を上げる工夫をすると良いでしょう。
次に脳のスイッチについて。
興奮状態ではなかなか眠れませんよね。
日中受けたストレスや肉体的な披露は脳を活動モードにしてしまいます。
特に最近では24時間営業のお店があったりするなど、光からストレスを受けやすい環境にあります。
そのため、脳は常に興奮状態、といっても過言ではありません。
脳のスイッチを入れるポイントは「単調」と「退屈」。
風景が変わらない真っ直ぐな道路を走っていると眠たくなることはありませんか?
これこそがまさに「単調」と「退屈」なのです。
刺激のない、つまらない状態を作ることで脳のスイッチがオフになり、深い眠りにつきやすくなります。
また、スマートフォンやパソコンの仕様はできれば睡眠前は控えるのがベスト。
さらに入眠時間を決めることで、体のリズムが整い、眠りやすくなります。
このようにちょっとした工夫で、夜はぐっすりと眠れるようになります。
アルツハイマー型認知症リスクを避けるためにも、質の高い睡眠を心がけてみませんか?
======
Slownetでブログやコメントを更新すると同じ趣味の仲間が見つかるかも!?人気のサークル情報などをお知らせするメールマガジンも受け取れる、Slownet会員登録はこちらから↓
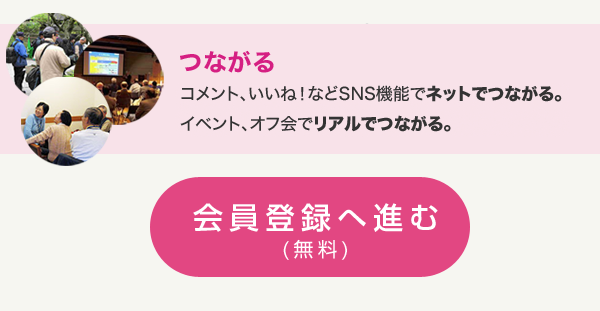
-
2025年5月22日
-
健康・美容
春の息吹を食卓へ! アスパラガスを味わおう!
春から初夏にかけて、店頭に並ぶ鮮やかな緑色が美しいアスパラガス。シャキシャキとした食感と、ほのかな甘みがたまらない、春を代表する野菜の一つですね。今回は、そんなアス...
-
2025年3月24日
-
健康・美容
苦みパワーで不調を改善
人間や動物は寒い冬を乗り切るため栄養分を体にため込む傾向があり、春になると、余分となった栄養分は老廃物となって外に排出されます。独特の苦みをもった春の山菜は、老廃物を外に出す成分を...
-
2025年3月10日
-
健康・美容
ランニングで脳を活性化!記憶力・集中力アップの秘訣
ランニングは単なる運動ではなく、脳を鍛える効果もあります。研究によると、ランニングによって記憶力や集中力を高める「海馬」や「前頭葉」が活性化し、新しい脳細胞が生まれることが分かって...
-
2024年8月1日
-
健康・美容
野菜・フルーツの老けない食べ方
老化の原因には、食事や生活習慣、ストレスなどさまざまな要因が挙げられますが、最近注目されているのが体の“酸化”。野菜や果物は、体の酸化を防いでくれる強い味方です。栄養素の長所を生か...
-
2024年7月1日
-
健康・美容
真夏に備えて、“汗活“をはじめよう!
気温が上昇すると、汗をかく機会や量も増えてきます。汗は体温調節などの重要な役割を担っており、“良い汗”をかくことも暑い時季を健康的に乗り切るポイントです。真夏に備えて“汗活”を始め...
-
2024年2月2日
-
健康・美容
めまいや頭痛の引き金に 気象病とその予防
低気圧が近づくと腰痛や関節痛がひどくなったり、季節の変わり目に片頭痛が出やすかったりしたことはありませんか? 天気の変化で不調を感じたら、それは「気象病」かもしれません。 「...

昼寝の常習犯だけどつい2、3回はふらりと寝ている感じだ。
朝5時に起床は定番、明るくなれば起きて食事作りタイムに入る毎日だね。